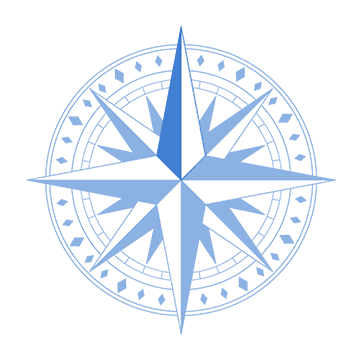経営戦略
M&Aの決め手
このコロナ禍で、銀行などから「企業(または事業)を買わないか?」という誘いが増えています。みなさんはどのような基準で買う・買わないを判断されているのか、その決め手となるものがあれば参考にいたしたくご質問いたしました。牟田さんの考え、またはご人脈から得た情報などあればお教えください。
業種:記載なし
年商:記載なし
牟田太陽より回答
「どこから話が来たのか」というのも重要なポイントです。私もそうですが、お客様を見てますと銀行さんからの話でM&Aをされた方は少ないです。
「同業で前から知っていたので御社に買ってほしい」「昔から取引があるので会社、社員をそのまま存続させてほしい」など、最近では、同業他社、取引先から話が来るパターンが多いです。
また、M&Aだけでなく、営業権譲渡であったり、落としどころも様々になっています。いまは後継者不在などで泣く泣く会社を手放す人も増えています。そこには金額ではなく「御社なら可愛い社員たちを任せられる」という社長同士の哲学・理念が似ているなど、価値観の類似が重要となっているようです。
(2022年8月17日 回答)
関連する記事
-
経営戦略
受注事業は、見込み事業と違って売り先は不特定で多数です。会社員なのか、主婦なのか学生なのか、などの対象を明確化してそこに対してどういうアプローチをしていくのか頭の中で明快に描くことができなければ商品は売れません。
業種:記載なし
年商:記載なし
-
経営戦略
復職前に一度面談をされてはいかがでしょうか。社長、総務、直属の上司と本人と話し合うことをお薦めします。こちらが3人で会うとなると圧迫感があるのであれば、総務と直属の上司で構いません。
業種:記載なし
年商:記載なし
-
経営戦略
まずは、プレジデント社から出ています私の「後継者という生き方」を読んでください。 「あるべき論」を書いた本というのは多いですが、多くの事例から親子双方の視点から書いてある本はありません。読んで絶対に損はありません
業種:お菓子をつくっている会社を継ぐ予定です
年商:おおよそ50億円