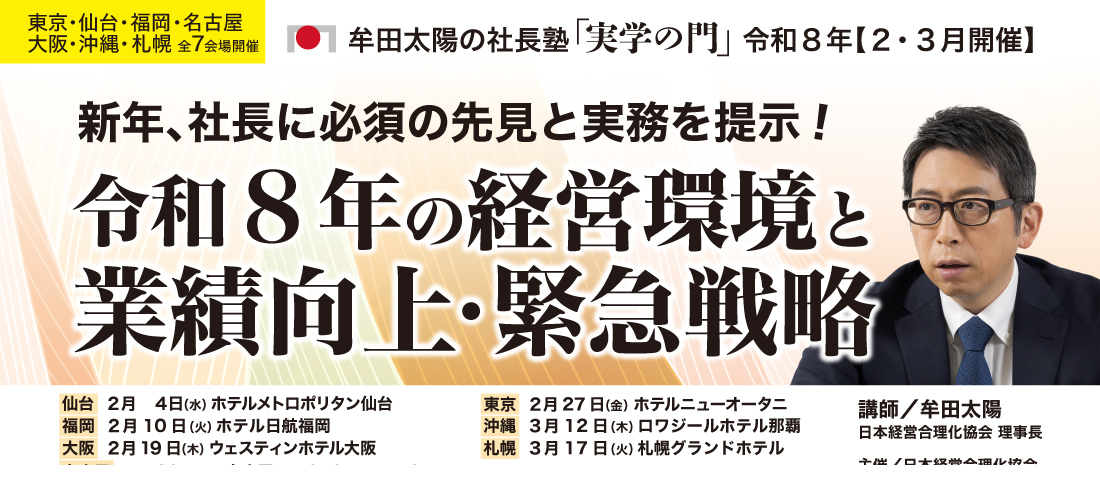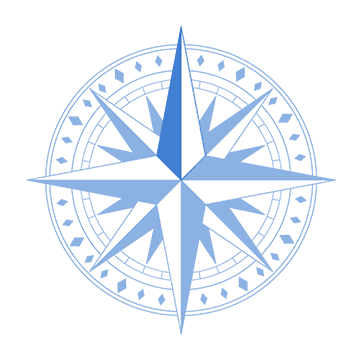経営戦略
パワハラのグレーゾーン
20年くらい勤続している40代の男性社員Aさんについて相談です。かつては一人で仕事をすることが多い部署だったために目立ちませんでしたが、数年前に管理部の課長へ異動させてから、部下の指導方法に問題が見られるようになりました。彼の求める水準に照らして部下の仕事に不十分なところがあると、彼が納得のできる受け答えを部下ができるまで、30分でも1時間でも延々と、理詰めの質問をたたみかけるのです。
彼が部下に求めていること自体は正論であり、声を荒げたり、暴言を吐いたりするわけではないのですが、部下たちは、いつもびくびくし、相当に気を遣って彼と話をしている状況です。たとえ業務指導であっても、相手の理解度に応じた指導をすべきであり、手短に話を終わらせるようにと注意をしましたが、彼は、自分も時間を無駄にはしたくないのに、部下がいい加減な仕事をしてそれを誤魔化そうとするから、このように指導をせざるを得ないと。さらに、社員にいい加減な仕事をされるのが社長の望みですか?と逆に言われました。
「人を見て法を説け」であることが、どうして彼は分からないのでしょうか。
業種:記載なし
年商:記載なし
牟田太陽より回答
ハラスメントというのは、これから一発退場となる危険性があることをキチンと教えなくてはいけません。
社内だけでなく、取引先に対してなど、たとえグレーゾーンであっても、録音など出てきてしまえば大きな問題として取り上げなくては会社の姿勢が問われてしまいます。それほど大きな問題です。
ましてや相手の方が鬱になってしまったらどう責任を取るつもりでしょうか。それほど様々な問題と絡み合っているのがハラスメントです。それほど経営は危機と隣り合わせなのです。いつまでも昭和の気分では会社を揺るがす問題にも発展しかねません。
(2023年12月21日 回答)
関連する記事
-
経営戦略
たとえ給料を上げても、その効果は一週間で終わります。お花畑みたいな夢ばかり語っても、それが給料に繋がっていなかったら効果はありません。そういったモノをキチンと書いた計画書をお作りになっていますでしょうか。社長の仕事は「伝えること」です。
業種:記載なし
年商:記載なし
-
経営戦略
都市部でのデータをもとに地方都市への店舗展開は王道と言えます。 ただ商品によっては、「都市部だからこそ売れる」商品もあります。 自社商品の特性は間違えてはいけません。 特にこのコロナ禍で店舗展開している多くの会社が、不採算店の店舗閉鎖をしました。 現在の最新の売り方は「オンライン・オフライン」の併用です。地方への展開は十分に検討した上で行ってください。
業種:小売業
年商:10億円
-
経営戦略
これは完全な謀反です。 ホールディングスの意味がなくなってしまいます。 また、おっしゃっているように大手との契約は金額は大きいですが、資金繰りの悪化などリスクも高いです。 私でしたら弟を主力子会社から外します。 兄弟仲どうこうという前に能力ない者に地位を与えると部下が不幸になってしまいます。
業種:建設業
年商:45億円